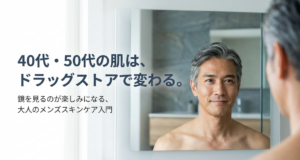![]() こんにちは。運営者の「シライヒロ」です。
こんにちは。運営者の「シライヒロ」です。
「着物トイレ 男」で検索されたということは、着物や袴での外出、特にトイレに関して大きな不安を感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。着物や袴でのトイレのやり方って、普段馴染みがないだけに、高価な衣装を汚してしまったらどうしようとか、着崩れが心配だとか、色々考えてしまいますよね。
特に、長着(着物)での小便(小)や大便(大)の方法、そして最高難易度とも言われる袴(はかま)を履いている時のトイレ手順は気になるところだと思います。また、洋式トイレと和式トイレでの違いや、万が一のために持っていくべき持ち物、例えばクリップの必要性、そして最も重要なトイレ後の着崩れの直し方まで、知っておきたいことは本当に多いですよね。
この記事では、そうした男性の着物でのトイレに関するあらゆる疑問に答えるために、具体的な手順からトラブル対処法まで、私の知識を総動員して詳しく解説していきますね。
- 長着(着物のみ)での基本的なトイレ手順
- 最難関である袴(はかま)着用時のトイレ手順
- トイレ後に必須の「着崩れ」を素早く直す方法
- 外出時に役立つ持ち物とトイレ選びのコツ
新品価格
¥594から
(2025/12/7 10:31時点)
着物男性のためのトイレの基本手順
まずは基本となる、着物(長着)だけを着ている場合のトイレ手順です。男性の着物は女性と違って「おはしょり」(着丈を調整する折り返し部分)がないため、構造は非常にシンプルです。
ですが、それは裏を返せば、着崩れを吸収してくれる「遊び」の部分がないということ。一度崩れるとごまかしが効かず、だらしなく見えがちです。だからこそ、動作は一つひとつ丁寧に行うのが本当に大事なコツですね。
長着での小便(小)のやり方
小便(小)の場合、いかに裾を汚さず、着崩れを最小限にするかがポイントです。立ち小便でも座る場合でも、基本的な手順は同じですよ。
1. 袖(そで)の処理
まず個室に入ったら、何よりも先に袖の処理です。着物の袖は意外と長くてボリュームがあるので、気づかないうちに便器や濡れた床に触れてしまう危険があります。
両方の袖を体の前で合わせ、帯と体の間にしっかりと挟み込みます。この時、落ちてこないように帯の下からくぐらせるようにして、奥まで深く差し込むのがコツです。もし後述する「着物クリップ」を持っているなら、両袖を合わせて胸元あたりにパチッと留めておくのが一番安全で、両手が自由になるので断然おすすめです。
2. 裾のめくり方(ピーリング)と固定
次に裾をめくります。ここで雑に全部まとめてガバッと掴んでまくり上げてはいけません。これが着崩れの最大の原因になります。
イメージは「ピーリング(皮むき)」。外側から「着物の裾」、次に「長襦袢(ながじゅばん)の裾」、最後に「肌着の裾」と、一枚ずつ丁寧にめくっていくのが正解です。こうすることで生地同士の摩擦が減り、スムーズにめくれますし、戻す時もシワにならずキレイに戻せます。
立ち小便の場合は、めくった全てのレイヤー(着物、長襦袢、肌着)を片手でしっかりと握りしめます。洋式に座る場合は、全てのレイヤーを左右に分け、両手でしっかりと保持します。
3. 用を足す際の注意点
立ち小便の場合、裾を握っている手と反対の手で用を足すことになりますが、この時、裾が緩んで落ちてこないように注意が必要です。また、飛び散り(跳ね返り)で裾を汚さないよう、いつもより少し便器に近づく意識を持つと良いかもしれません。
4. 戻す際の手順
用を足した後は、慌てずに。めくった時とは逆の順序で、「肌着」「長襦袢」「着物」の順に一枚ずつ丁寧に下ろしていきます。この時、生地のシワをパンパンと軽く手で張りながら整えて下ろすのが、キレイに戻すコツですね。最後に袖のクリップや挟み込みを解除するのを忘れないようにしてください。
長着での大便(大)のやり方
大便(大)の場合は、小便時よりもさらに大胆に裾を持ち上げ、その状態を長時間キープする必要があります。難易度は上がりますが、手順自体は合理的です。
1. 裾のめくり方と固定(最重要)
手順は小便時とほぼ同じですが、裾をめくる高さが全く違います。座った際にお尻が完全に露出し、着物が便器に触れないようにするため、着物、長襦袢、肌着のすべてを、帯よりも高い位置、できれば胸の下あたりまで一気に持ち上げます。
この「高く持ち上げた状態」を手で押さえ続けるのは現実的ではありません。ここで便利なアイテムの出番です。
予備の「腰ひも」や「クリップ」が活躍
高く持ち上げた裾束の上から、予備の「腰ひも」を巻き、胸の下あたりで仮留め(蝶結びなどでOK)しておくと、両手が完全に自由になり非常に楽です。これが一番確実な方法かなと思います。
もし腰ひもがなければ、着物クリップを複数(できれば3〜4個)使って、持ち上げた裾を帯の上部や胸元あたりに固定することもできますよ。
2. 座り方と戻し方
裾を固定したら、いよいよ座りますが、ここでも次のセクションで解説する「浅く座る」テクニックが必須です。深く座って帯を押し上げないように、細心の注意を払ってください。
用を足し終わったら、仮留めした腰ひもやクリップを慎重に外します。そして、小便の時と同じように「肌着」「長襦袢」「着物」の順に、一枚ずつ丁寧に下ろしていきます。ここでサボると、中で生地が団子状になってしまい、後で直すのが非常に大変になりますからね。
洋式トイレで浅く座るコツ
これは長着でも袴でも共通する、着物トイレにおける最重要テクニックだと私は思っています。これをマスターするだけで、トイレ後の着崩れが劇的に減ります。
帯の結び目を守る
洋式トイレに座る際、絶対に深く腰掛けてはいけません。
なぜなら、深く座ると背中にある帯の結び目(特に角帯の「貝の口」のように硬く角張った結び目)が、便座のフタに強く押し付けられてしまいます。その結果、帯全体がテコの原理で上へずり上がってしまい、これがトイレ後に一番目立つ「最悪の着崩れ」の原因になるんです。兵児帯(へこおび)のような柔らかい帯でも、押し付けられるとせっかくの結び目の形が崩れてしまいますからね。
帯の「ずり上がり」に注意
着崩れを防ぐため、必ず便座の縁に「浅く腰掛ける」ことを徹底してください。目安としては、「お尻が半分乗るか乗らないか」くらいの位置です。帯がフタに触れない位置を厳守するのが大事です。
不安定な場合の対処法
浅く座ると、当然ながら体は少し不安定になります。特に大便(大)で裾を胸元まで上げている状態だとバランスが取りにくいかもしれません。その場合は、片手で個室の壁や(清潔そうであれば)手すりなどを軽く支えて、体がふらつかないようにすると安心です。
和式トイレを避けるべき理由
結論から言うと、着物や袴の時は、和式トイレは可能な限り、絶対に避けるべきです。もし選択肢があるなら、迷わず洋式を選んでください。
理由は主に2つあります。
1. 物理的な汚れのリスク
和式トイレは、裾が床に触れるリスクが非常に高いです。蹲踞(そんきょ)の姿勢をとるため、洋式よりもさらに高く裾をまくり上げ続けなければならず、少し気を抜くと長い裾や袖が床に触れてしまいます。また、バランスを崩した際に手をついて、袖を汚してしまうリスクも考えられます。
2. 水シミ(跳ね返り)のリスク
和式トイレは構造上、フタができず水の飛沫(ひまつ)が飛び散りやすいです。これが裾や着物についてシミになる危険性があります。
特に「絹(シルク)」の着物は要注意
高価な正絹(しょうけん)の着物は、水シミが非常に目立ちやすく、一度シミになると素人ではまず取れません。専門的なシミ抜きが必要になり、高額な費用がかかる可能性もあります。そのリスクを冒してまで和式を選ぶメリットは一つもない、と私は思います。
万が一、和式しか無い場合の対処法
もしどうしても和式トイレしかない場合は、覚悟を決めて臨むしかありません。裾は「これでもかというほど高く」まくり上げ、クリップや腰ひもで完璧に固定します。袖も同様に、帯に挟むだけでなくクリップで留めるなど、二重三重の対策をしてください。そして、全ての動作をゆっくりと、細心の注意を払って行うことが重要です。
トイレ後の着崩れの直し方
どんなに気をつけても、裾をまくり上げたり座ったりという動作をすれば、多少の着崩れは起きてしまうものです。大切なのは「起きたら直す」と割り切ること。トイレの個室(特に後述する姿見がある場所)は、着崩れを直す絶好のチャンスです。
トイレ後に確認すべきは、「帯」「衿元」「裾」の3大ポイントです。
着崩れ修復の基本
トイレでの着崩れは、裾を「上」にまくり上げたり、帯が「上」に押し上げられたりすることが直接的な原因です。したがって、修復作業は、その原因となった動作の「逆」=「下」へ戻す動作が基本となります。論理的に考えれば難しくありません。
1. 帯(おび)の直し方
典型的な状態: 帯がウエスト(正しい腰骨の位置)まで上がってしまっている。
修復方法: 帯の上縁(うわべり)に左右の親指を差し込み、他の指は帯の下に添えます。そして、少し体重をかけるようにして、帯全体を「下」へ(正しい腰の位置まで)グッと押し下げます。この時、一気に下げるのではなく、少しずつ均等に下げるのがコツです。最後に帯の中のシワを伸ばすように、指を左右に滑らせて整えます。
2. 衿元(えりもと)の直し方
典型的な状態: 胸元が緩みすぎている。衿が左右非対称になっている。
修復方法: 裾をまくり上げる動作で、着物全体が上に引っ張られることが原因です。衿元が緩んでいると、だらしなく見えてしまい、大人のメンズが持つべき清潔感も損なわれてしまいますからね。ここはしっかり直します。
まず、緩んだ上前(うわまえ:表側)を少し開きます。その中にある下前(したまえ:内側)の衿先を掴み、「左」方向(内側)へキュッと引きます。これで内側が締まります。次に、上前を元に戻し、その衿先を「右」方向(内側)へ引きます。これで胸元がスッキリと整います。内側から直さないと根本的な解決にならない、というのがポイントです。
3. 裾(すそ)の直し方
典型的な状態: 裾が広がってだらしなく見える(裾つぼまりでない)。まくり上げたものを雑に戻すとこうなりがちです。
修復方法: 男性の着物は、裾がすぼまっている「裾つぼまり」のシルエットが美しいとされています。これを復活させます。着物の懐(ふところ)から手を入れます。まず下前(左太もも付近)の生地を掴み、「左下」方向へ引きます。次に上前(右太もも付近)の生地を掴み、「右下」方向へ引きます。これで裾がキュッと締まり、粋なシルエットが戻ります。
袴の着物トイレ 男性の完全攻略法
さて、ここからは応用編、最高難易度とも言われる「袴(はかま)」を着用している場合のトイレ攻略法です。袴は着物の上からもう一枚履くため、手順が複雑になり、難易度が格段に上がりますが、手順さえ覚えてしまえば大丈夫です。落ち着いていきましょう。
袴(はかま)のトイレ手順
まず混乱しやすいポイントですが、袴のトイレには大きく分けて2つの方法があります。
馬乗袴と行灯袴
袴には、中でズボンのように分かれている「馬乗袴(うまのりばかま)」と、スカート状の「行灯袴(あんどんばかま)」があります。ですが、トイレに関しては、どちらのタイプでも基本的な手順は同じです。馬乗袴(ズボンタイプ)でも、用を足す際は結局まくり上げるか脱ぐかになるので、難易度は変わりません。
この2つの方法は、どちらかが正解というわけではなく、目的(小か大か)によって明確に使い分ける必要があります。これを間違えると、ほぼ確実に失敗すると思ってください。
【目的別】袴トイレの2大メソッド
目的別に、使用すべきメソッドを明確に区分します。この使い分けが非常に重要ですね。
| 目的 | 推奨メソッド | 具体的な手順の概要 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 小便(小) | リフティング(持ち上げ)法 | 袴・着物・長襦袢の裾を前から持ち上げる | 中 |
| 大便(大) | アンタイイング(紐解き)法 | 袴の後ろ紐を解き、着物をまくり上げる | 高 (最難関) |
大便(大)のために「リフティング法」を試みると、まず間違いなく窮屈で失敗しますし、小便(小)のために「アンタイイング法」を行うのは手間がかかりすぎ、着崩れリスクも高すぎます。
袴での小便(小)のコツ
小便(小)の場合は、「リフティング法」を使います。これは袴も着物も一緒にまくり上げる方法です。
3層の生地をめくる
手順は長着の時と似ています。前から手を入れて、一番外側にある「袴の正面の裾(前裾)」を持ち上げます。次に、その下にある「着物の裾」を持ち上げます。最後に、一番下にある「長襦袢の裾」を持ち上げます。
保持する際の最重要点
この3層の生地の束を、片手でしっかりと握りしめます。ここで非常に重要なコツがあります。
一番内側にある「長襦袢の裾」をしっかり掴んでいれば、重い袴の裾が途中で落ちてくることはありません。一番軽く滑りにくい長襦袢を掴むことで、その上にある重い着物と袴の生地が摩擦で滑り落ちるのを防ぐ、というロジックです。外側の袴だけを持とうとすると、重さで滑り落ちてしまうので注意してください。
用を足したら、逆の手順(長襦袢→着物→袴)で丁寧に下ろします。この時、袴のプリーツ(ひだ)が崩れないように整えながら下ろすのがポイントです。
袴での大便(大)のやり方
これが男性和装で最も難しい技術、「アンタイイング法」です。手順が複雑なので、事前の理解と、できれば自宅での練習が強く推奨されます。
最大の注意点:紐(ひも)の処理
この方法で最も危険なのは、解いた袴の長い後ろ紐を床に落として汚してしまうことです。紐は非常に長いので、以下の手順を厳守してください。
1. 後ろ紐を解き、帯に挟む(最重要)
まず、背中側にある袴の後ろ紐を一度解きます。解いた長い紐が床に落ちて汚れないよう、すぐに帯の間(袴と着物の隙間)に、紐の先端から根本までしっかりと押し込みます。これが最重要プロセスです。
2. 着物と長襦袢をまくり上げる
次に、袴の中にある着物と長襦袢を一緒に捲り上げます。これも落ちてこないように、帯に挟み込みます。長着の大便の時と同様、帯の下からくぐらせるように挟み込むとより安全ですね。
3. しゃがみ方と注意点
袴の裾が床に付かないよう、少し捲り上げて手で押さえます。この状態で下着を下ろし、洋式トイレに「浅く」しゃがみ込みます。この時点で下半身は(袴の後ろ側が開いているため)フリーな状態になります。
この一連の手順は、慣れないと本当に着物や袴が予期せぬ方向に広がり、汚してしまう可能性があります。動作は一つひとつ、ゆっくりと、確認しながら行う必要があります。
用を足した後は、逆の手順で着物を下ろし、最後に袴の紐を結び直します。この「結び直し」も着付けの技術が必要なので、やはり外出前に一度は練習しておくと安心ですね。
袴の着崩れ修復方法
袴の場合、着崩れの問題は「袴の中」で起きています。特に大便(大)で「アンタイイング法」を使った後は、内部で着物がずれている可能性が非常に高いです。
直し方は、袴の脇のあき(スリット部分)から手を入れるのが基本です。ここしか袴内部にアクセスできる場所がありませんからね。
1. 袴内部の着物を直す
脇のスリットから手を奥まで入れ、中の着物の裾(上前と下前)を探します。お尻や太もも周りで生地がたるんでいる感覚があると思うので、それを掴んで「下」にグイッと引っ張り、たるみを整えます。
2. 帯の位置を直す
もし帯が上がっている場合は、袴の上から直すのは困難です。同様に脇から手を入れて帯を直接掴み、「下」へ(正しい位置へ)押し下げます。
3. プリーツ(ひだ)を整える
最後に、袴の紐を結び直すか(または緩んでいないか確認し)、袴全体を整えます。袴の前後を軽く持ち上げて空気を入れ、生地を下に落とす感じで「バサッ」と振りさばくと、プリーツ(ひだ)がキレイに戻りますよ。
最大の予防策は「裾を踏まない」こと
袴の着崩れは、トイレだけでなく階段の上り下りでも発生します。裾を踏んでしまうのが原因です。階段を登り降りする際は、袴の前の裾を少し持ち上げる癖をつけると、着崩れをかなり予防できますよ。
必須の持ち物とクリップ

着物での外出時、特にトイレ対策として持っていると非常に役立つ、というか私にとっては「無いと不安」なアイテムがあります。
着物トイレの三種の神器
- 着物クリップ(必須)
袖を留めたり、まくった裾を帯に仮留めしたりするのに使います。これが無いと難易度が跳ね上がります。最低2個、できれば3〜4個あると万全です。 - 腰ひも(予備)(推奨)
大便(大)の際に、まくった裾すべてを縛るのに非常に役立ちます。着付けに使うものでOKです。 - ハンカチ・手ぬぐい(必須)
手を拭くのはもちろんですが、万が一の水はねをすぐに拭き取れるよう、吸水性の高いものを持っていると安心です。大人の男性として、上質なメンズハンカチを一枚持っておくと、こういう時にも役立ちますね。
これに加えて、便座や手すりを拭ける「除菌シート」もあると、さらに安心感が増しますね。
クリップの代用品は?
専用の「着物クリップ」がベストです。挟む部分がゴムになっていて生地を傷めにくいですし、保持力も高いです。
もし無ければ、「挟む力が強すぎない洗濯バサミ(ギザギザがないもの)」や「大型のペーパークリップ」でも代用は可能です。ただし、洗濯バサミは生地に跡がつく可能性がありますし、小さなクリップは重い生地を留めきれないことがあるので、注意は必要ですね。錆が移るのも怖いですし…やはり専用品が一番安心かなと思います。
着物トイレ 男の不安を自信に
最後に、着物トイレの不安を解消するための「場所選び」のコツです。どのトイレを選ぶかが、成功の半分を占めると言っても過言ではありません。
私が着物で外出する際に、トイレを選ぶ基準は以下の3つです。
1. 絶対条件:洋式トイレ

これはもう解説した通りですね。和式はリスクが高すぎます。必ず洋式を選びます。
2. 推奨条件:清潔で「広い」個室
着物や袴の裾をまくり上げたり、それを保持しながら体を回転させたりするには、ある程度のスペース(個室の広さ)が必要です。狭い個室だと、壁に袖や裾が触れてしまうかもしれません。
デパートやホテルのロビー、比較的新しい商業施設のトイレは、広めに作られていることが多いですね。(※多目的トイレは、本当に必要な方が優先ですが、広さという点では理想的です。)
3. 最重要条件:全身が映る鏡(姿見)の有無
私にとって、これが最も重要なポイントです。先ほど解説した「着崩れの修復術」は、鏡なしでは不可能です。特に帯の位置や衿元の緩みは、自分では気づきにくいものです。
衿元、帯の位置、裾のラインを正確に確認できる「全身鏡」が、トイレの個室内またはパウダールームに設置されている場所。ここを事前にチェックしておくと、安心してトイレに行けます。
解説した手順、特に「袴での大便(アンタイイング法)」は、テキストで読むと非常に複雑に感じられたかもしれません。でも、最大の対策は「練習」です。着物は「習うより慣れろ」な部分も大きいですからね。
ぜひ外出する前に一度、ご自宅のトイレで「袖を固定し、裾をまくり上げ、浅く座り、元に戻し、鏡の前で着崩れを直す」という一連の流れをシミュレーションしてみてください。
このガイドを武器に、トイレの不安を克服し、自信を持って着物での外出を楽しんでくださいね。